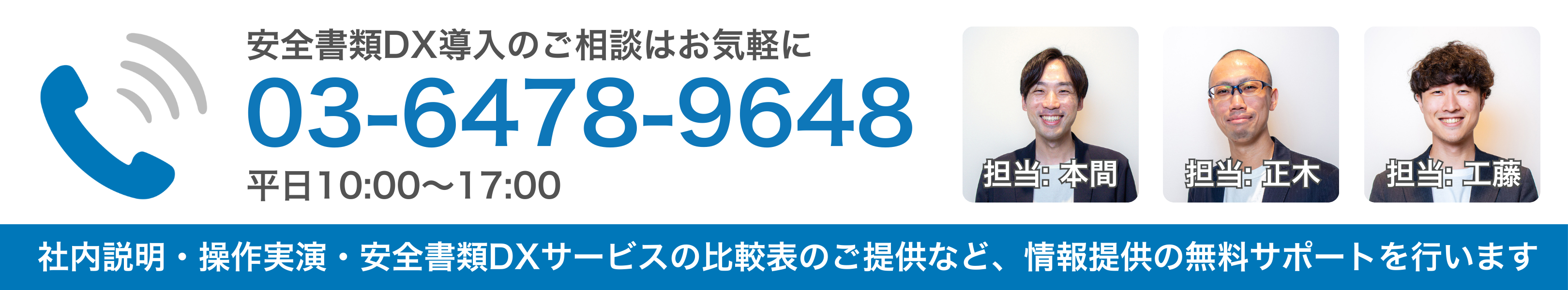特定建設業者は施工体制台帳と同様に、施工体系図を作成して各協力会社の施工分担関係が一目でわかるようにすることが建設業法によって定められています。
ここでは最も代表的かつ広く使用されている「全建統一様式 第4号」を定型として施工体系図の書き方について解説していきます。
なお、項目は他の書式であってもほとんど変わらないため、その他安全書類の書式の施工体系図を作成する方も問題なく参照していただけます。
目次
施工体系図とは
施工体系図とは、作成された施工体制台帳や再下請負通知書に基づいて各協力会社の施工分担関係が一目で分かるようにした図で、元請企業(=発注者から直接建設工事を請け負った建設企業)が作成します。
主に以下の3点を目的として作成されています。
- 協力会社も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握するため
- 建設工事の施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にするため
- 技術者の適正な配置の確認のため
施工体系図の作成義務と掲示の必要性
施工体系図の作成義務のある工事は、施工体制台帳の作成義務のある建設工事と同様で、以下のように定められています。
また掲示場所に関しては公共工事・民間工事で異なりますので注意してください。
- 公共工事
いつ:発注者から直接請け負った公共工事を施工するために請負契約を締結したとき
どうする:工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない(公共工事入札契約適正化法第15条第1項) - 民間工事(公共工事以外の建設工事)
いつ:発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した請負契約の総額が5,000 万円(建築一式工事にあっては、8,000 万円)以上となったとき(令和6年12月改正)
どうする:工事関係者が見やすい場所に掲げなければならない(法第24条の7第4項)
新たに工事企業が追加された場合や体制に変更が生じた場合は、すみやかに施工体系図を差し替える必要があります。
施工体系図の保管期間
施工体系図は営業に関する図書として、営業所ごとに引き渡しから10年保存することが義務付けられています。(建設業法施行規則第26条第5項)
施工体系図の記入例・書き方
施工体系図では協力会社までを含め、工事に関わる建設企業がどのような分担で施工するのかを、一目で分かるようにした樹形図の形で記載します。
なお再下請負通知書、下請負業者編成表と記載内容がほぼ同じなので、既に作成していればそちらを参考に記入していただいて構いません。
左側部分の各項目と記入例・書き方

発注者名
工事を発注した企業名を記入します。
工事名称
元請企業が担当する工事内容について記入します。
元請名・事業者ID
工事を担当する元請企業名を記入します。また建設キャリアップシステムに登録されている場合には当該事業者IDを記入します。
監督員名
発注者より通知された監督員名をフルネームで記入します。
監理技術者・主任技術者名
監理技術者と主任技術者の名前をフルネームで記入します。
監理技術者補佐名
監理技術者補佐名の名前をフルネームで記入します。
一定の条件を満たし、監理技術者が複数の現場を兼任する場合に監理技術者補佐を配置します。
専門技術者名・担当工事内容
自社が担当する工事に取り掛かる際、内容によっては別の専門工事が発生し自社で直接施工する場合があります。その場合「現場ごと」「担当する業種ごと」に専門技術者を配置する必要があります。
専門技術者は『主任技術者』の条件を満たしていることが必要です。
したがって『資格内容』の欄には前述した『主任技術者』の条件を記入してください。
担当工事内容は、発生した専門工事の内容を記入します。
統括安全衛生責任者
元請企業の統括安全衛生責任者の名前をフルネームで記入します。統括安全衛生責任者とは、協力会社を含めて労働者が常時50人以上(ずい道等の工事、圧気工事、一定の橋梁工事においては30人以上)就労する作業所において元請企業が選任するものです。(労働安全衛生法第15条、同法施行令第7条)
副会長
元請企業以外の協力会社から選出された者の名前をフルネームで記入します。共同企業体では、企業体を形成している事業者の名前を記入します。
元方安全衛生責任者
元方安全衛生責任者の名前をフルネームで記入します。
元方安全衛生管理者とは、統括安全衛生責任者が選任される事業所に置かれ、技術的事項の管理、統括安全衛生責任者の補佐を行なう者のことです。(労働安全衛生法第15条の2)
書記
災害防止協議会の内容を記録する者の名前をフルネームで記入します。
右側部分の各項目と記入例・書き方

工期
工事内容に必要な工期を記入します。『自』の欄には工事開始日を、『至』の欄には工事終了日を記入してください。
企業名・事業者ID
元請企業と協力関係にもとづく契約を結んだ企業名(1次請)を記入します。
また建設キャリアアップシステムに登録している場合には、事業者IDを記入します。
縦は元請企業と協力関係にもとづく契約を結んだ企業(1次請)、横はその企業と協力関係にもとづく契約を結んだ企業(2次、3次)を記入します。
代表者名
代表者名を記入します。
建設業許可番号
許可業種の許可番号を記入します。「国土交通大臣許可」か「◯◯県知事許可」のどちらかを、次に「一般建設業=般」「特定建設業=特」のどちらかを、最後に番号を記入しましょう。
※「特定建設業」は自社が元請である場合に必要なものなので、基本的には「一般建設業」を選択してください。
特定専門工事=下請代金の合計額が4,500万円未満
工事内容
担当する工事内容を記入します。
特定専門工事該当の有無
特定専門工事=下請代金の合計額が4,500万円未満の「鉄筋工事」及び「型枠工事」である場合には「有」、それ以外は「無」で選択します。
安全衛生責任者
安全責任者名をフルネームで記入します。安全衛生責任者とは、労働安全衛生法に定められている事業所での安全を管理する人のことです。
選任する際の資格はありませんが、安全衛生に関する特別教育を受けた者かつ現場に常駐する現場代理人・主任技術者または職長などによる選択が推奨されています。
安全衛生責任者は労働災害を未然に防ぐためにも、初めて業務に従事する場合や業務従事後に一定期間経過した際は、安全衛生に関する教育、講習を実施するようにしましょう。
主任技術者
主任技術者の名前をフルネームで記入します。主任技術者とは工事現場における技術的な管理をする人のことです。そのため主任技術者には一定水準以上の知識や経験が無ければなりません。
ここで注意したいのは、公共性のある重要な工事で元請企業との契約額が4,500万(建築一式工事の場合は9,000万)以上の場合は「専任」つまり現場に常駐する必要があるということです。(令和6年12月改正)
専門技術者・担当工事内容
専門技術者の名前をフルネームで記入します。自社が担当する工事に取り掛かる際、内容によっては別の専門工事が附帯し自社で直接施工する場合があります。
その場合、「現場ごと」「担当する業種ごと」に専門技術者を配置する必要があります。専門技術者は『主任技術者』の条件を満たしていることが必要です。
担当工事内容では、附帯工事の内容を記入します。
工期
自社の工事内容に必要な工期を記入します。
さいごに
施工体系図の書き方について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
安全書類(グリーンファイル)で記入していることと同じ内容が多いため、要点を押さえておけばそこまで作成は難しくないです。他の安全書類の書き方も解説していますので、気になる方は是非ご覧ください!
施工体制台帳の書き方と記入例|様式から作成義務まで解説
再下請負通知書の書き方を記入例を解説|下請・協力会社を管理する
作業員名簿の記入例や書き方を日本一詳しく解説!社会保険もミスなく作成
安全書類業務の効率化ならGreenfile.work
安全書類DXサービス『Greenfile.work(グリーンファイルドットワーク)』なら、施工体系図はもちろん、作業員名簿、施工体制台帳、再下請負通知書など、あらゆる安全書類をオンライン上で効率的に作成・管理できます。
Greenfile.workの公式HP(資料請求)は こちらすぐに話が聞きたい方は、以下の電話番号まで気軽にお電話ください。
(Greenfile.work運営元のシェルフィー株式会社の電話番号です)